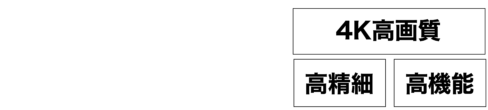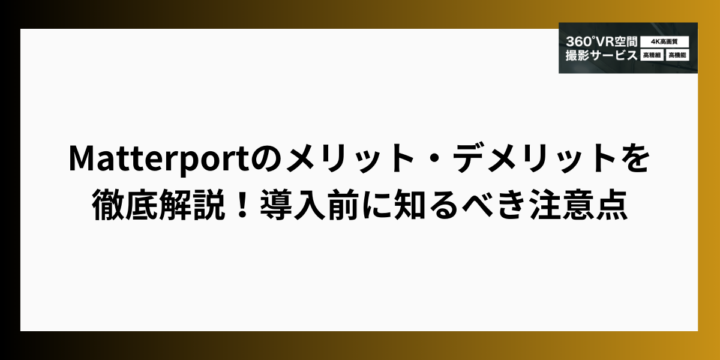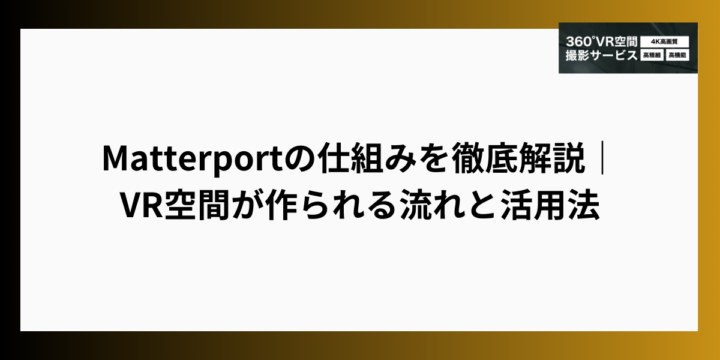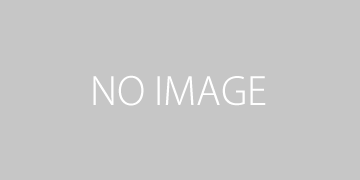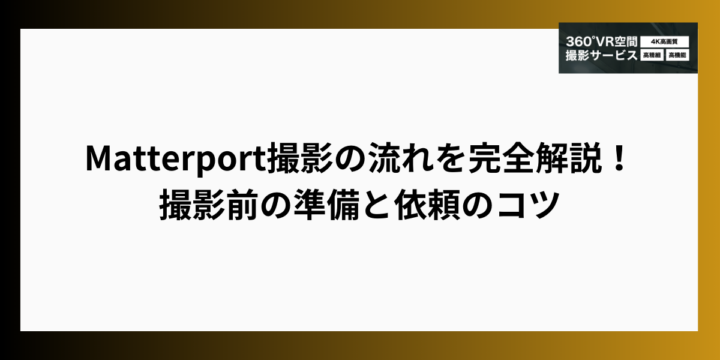来館者増に直結!美術館・博物館でのMatterport活用事例と魅力とは
美術館や博物館の展示をもっと多くの人に届けたい。
遠方の人や身体的な理由で来館が難しい方にとって、現地での鑑賞は簡単ではありません。
そこで注目されているのが、展示空間を3Dで再現できる「Matterport」です。導入すれば、リアルな展示体験をオンラインで提供でき、来館者の幅を広げられます。
この記事では、美術館・博物館でのMatterportの活用方法や導入事例、具体的なメリットを解説します。来館者拡大やデジタル展示を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
美術館・博物館でのMatterport活用とは?
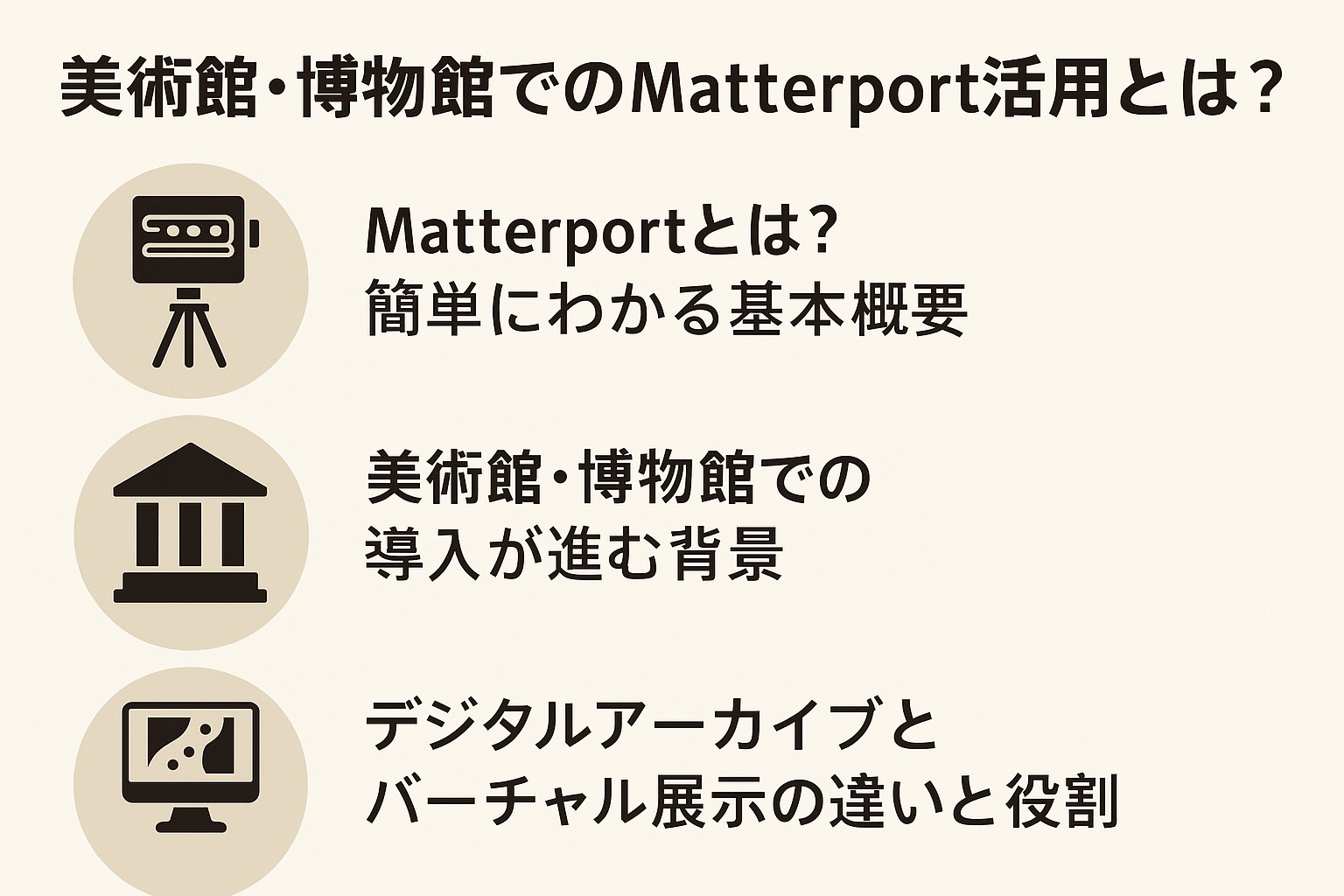
近年、デジタル技術の発展により、美術館や博物館でもさまざまな新しい取り組みが進んでいます。その中で注目されているのが、3D撮影と空間データの技術を組み合わせた「Matterport(マーターポート)」の活用です。
Matterportは、空間そのものを高精度にスキャンして、バーチャルで再現する技術です。建物の内部を自由に見て回れるような3Dモデルを、誰でも手軽にオンラインで体験できます。展示空間の保存、鑑賞体験の拡張、遠隔地からのアクセスなど、多くのメリットがあります。
美術館や博物館では、展示内容を「デジタルで残す」「世界中の人に公開する」ために、この技術の導入が進んでいます。
Matterportとは?簡単にわかる基本概要
Matterportとは、空間全体を3Dカメラでスキャンし、360度の立体データとして再現できるサービスのことです。専用のカメラやスマートフォンを使い、部屋や建物を撮影するだけで、リアルな空間がデジタル上に立体的に再現されます。
この技術を使うと、Web上で空間を自由に見渡したり、移動したりできるようになります。まるで現地にいるかのようなリアルな感覚を得られることが特長です。撮影された空間には、以下のような情報も追加できます。
- ・画像や文章を埋め込んだ「タグ」
- ・音声ガイドや動画による解説
- ・複数フロアの連続的な移動
これらの機能により、展示作品の解説やストーリーの補足など、体験を豊かにする演出が可能です。空間の再現だけでなく、観覧者との対話を深めるメディアとしての可能性も秘めています。
Matterportは、美術館や博物館の展示をデジタル化し、世界中の誰もが鑑賞できる形に変える強力なツールです。
美術館・博物館での導入が進む背景
美術館や博物館でMatterportの導入が広がっている背景には、複数の社会的・技術的な要因があります。特に影響が大きかったのは、新型コロナウイルスによる行動制限です。施設に訪れる人が減り、「どこにいても楽しめる展示」の必要性が高まりました。
また、文化資産や貴重な展示物を「未来に残す」動きも進んでいます。気候変動や災害、経年劣化などにより、物理的な保存だけでは不安があるため、デジタルでの記録が強く求められるようになりました。
さらに、以下のようなニーズの高まりも要因です。
- ・海外からの来館が難しい層に向けたオンライン公開
- ・教育機関や研究機関との連携による教材活用
- ・来館前の「予習」としての体験提供
このように、社会の変化と技術の進化が組み合わさり、美術館・博物館におけるMatterport活用は加速しています。
デジタルアーカイブとバーチャル展示の違いと役割
美術館や博物館でのデジタル化には、「デジタルアーカイブ」と「バーチャル展示」という2つの異なるアプローチがあります。それぞれの役割を理解することは、Matterportの活用を考える上で重要です。
まず、デジタルアーカイブとは、文化財や展示品を保存・記録する目的でデジタル化することです。主に内部の研究や記録保存に使われます。静止画、図面、解説文などが中心で、第三者に公開することが前提ではありません。
一方、バーチャル展示は、来館者やインターネット利用者が「体験」できることを重視した公開型コンテンツです。Matterportはこのバーチャル展示に非常に適しており、以下のような特徴があります。
- ・立体的に再現された空間を移動しながら観覧できる
- ・クリックすると解説が表示されるインタラクティブな構成
- ・スマートフォンやパソコンで誰でも簡単にアクセス可能
このように、アーカイブが「残す」ことに特化しているのに対し、バーチャル展示は「見せる」ことを重視しています。
Matterportは、展示空間をそのまま「伝える」手段として、バーチャル展示の中核を担っています。
美術館・博物館でMatterportを活用するメリット

Matterportの導入により、美術館や博物館はこれまでにない価値を提供できます。来館者の体験を拡張するだけでなく、施設側にも大きな利点があります。ここでは、代表的なメリットを4つ紹介します。
物理的な来館が難しい人にもアプローチできる
Matterportを使うことで、施設に足を運ぶことが難しい人々にも展示を届けることが可能になります。移動が困難な高齢者や障がいのある方、地方や海外に住んでいる方に対しても、等しく鑑賞の機会を提供できます。
バーチャル展示はインターネット環境があれば、誰でも利用できます。空間を自由に歩き回れるため、実際の来館と同じような感覚を味わえます。映像やテキストによる解説を加えれば、より深い理解につながります。
アクセスに制限がある人でも、デジタル技術によって「鑑賞する権利」が守られるようになりました。
展示空間の保存と記録に最適
Matterportは展示そのものだけでなく、展示空間全体を記録できる点が大きな特徴です。展示会は期間限定であることが多いため、内容を後から振り返ることは簡単ではありません。ですが、Matterportなら空間をそのままの形で保存できます。
保存された3D空間は、研究資料や再展示の参考資料としても有効です。以下のような活用が考えられます。
- ・展示構成や動線の再検討
- ・将来のリニューアルに向けた記録
- ・展示作品の配置と演出方法の確認
画像や映像では表現しきれない「空間の流れ」や「雰囲気」まで記録できるため、展示の質の向上にも貢献します。
Matterportによって、展示空間は一時的なものではなく「資産」として蓄積できるようになります。
多言語対応やグローバル展開が可能
インターネット上に公開できるMatterportの3D展示は、世界中からアクセス可能です。しかも、表示されるテキストやガイドを多言語対応にすれば、海外の鑑賞者にも十分な情報を提供できます。
例えば、以下のような言語対応が可能です。
- ・日本語と英語の切り替え表示
- ・中国語やスペイン語への翻訳テキストの表示
- ・音声ガイドの多言語収録
こうした機能により、海外観光客や外国語を話す在住者にも対応できます。パンフレットや現地ガイドに頼らずとも、正確で丁寧な案内が可能になります。
Matterportは、美術館・博物館の国際的な発信力を高めるための強力なツールです。
来館前のバーチャル体験による集客力アップ
Matterportを使えば、来館前に展示内容を一部体験してもらうことができます。この「バーチャル予習」により、実際に訪れたいという意欲を高める効果が期待できます。
実際の空間を見せることで、以下のような印象を与えられます。
- ・施設が広くて見応えがある
- ・作品の展示方法が魅力的である
- ・安全で快適な観覧ができそう
とくに初めて訪れる人にとっては、事前に雰囲気をつかめることが安心感につながります。家族連れや学校団体にも有効な施策です。
バーチャル体験を通じて来館意欲を高めることで、実際の来場者数の増加にもつながります。
Matterportを活用した美術館・博物館の成功事例

Matterportは、多くの美術館・博物館で実際に導入されており、幅広い分野で成果をあげています。ここでは、国内外の導入事例や常設展・企画展での活用、さらに教育や研究との連携について紹介します。
国内外の代表的な導入事例紹介
Matterportは、世界中の文化施設で広く活用されています。とくに、海外ではバーチャル展示の先進事例が多く、日本国内でも少しずつその動きが広がりを見せています。
代表的な導入事例には、以下のような施設があります。
- ・米国:スミソニアン博物館がオンライン展示で3D体験を提供
- ・英国:ナショナル・ギャラリーが特別展の再現に使用
- ・日本:福井県立恐竜博物館がバーチャル見学ツアーを公開
これらの事例では、実際に施設を訪れたような没入感があり、オンラインであっても展示の魅力を伝えることに成功しています。スミソニアンでは、展示物に関する解説を3D空間内に埋め込み、教育的価値も高めています。
Matterportの導入により、施設の魅力をより多くの人に届けることが実現しています。
常設展示だけでなく企画展でも活躍
Matterportは、期間限定の企画展でも大きな効果を発揮します。展示が終了したあとも、その空間をバーチャルで残すことができるため、記録としてだけでなく、来場できなかった人の鑑賞機会としても価値があります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
- ・現地開催が困難な国際的な展示を、バーチャルで全世界に配信
- ・人気展覧会を終了後も「常設展示」として公開し、継続的に集客
- ・他館と連携し、企画展をオンラインで巡回させる仕組みを構築
短期間で終わってしまう企画展は、記録が残りにくいという課題があります。しかし、Matterportなら空間ごと記録・公開が可能で、展示の価値を長く保つことができます。
企画展とMatterportの相性は非常に良く、コンテンツ資産化にもつながります。
教育・研究分野での活用方法
Matterportは、美術館や博物館だけでなく、教育や研究の現場でも高く評価されています。展示空間をそのまま教材として活用できるため、学びの幅が広がります。
具体的な活用例は以下の通りです。
- ・小中高校の授業で、展示空間を使ったリモート学習
- ・大学や専門機関での文化財研究における空間構成の分析
- ・ワークショップでの参加型体験コンテンツの提供
たとえば、学校の授業でMatterportを使えば、遠足や見学に行けない場合でも、生徒が施設内を「歩く」ように学習できます。また、文化財の保存状態を3Dで記録することで、経年劣化の比較分析も可能になります。
Matterportは、教育と研究の現場においても、新しい学びと発見を生み出すツールとなっています。
Matterportで実現できるデジタル展示の具体例

Matterportを活用した展示では、従来のオンライン展示では不可能だった「空間の質感」や「多層的な情報提供」が可能になります。ここでは、実際にどのようなデジタル展示が実現できるのか、その具体的な内容を紹介します。
高解像度3Dスキャンで作品の質感まで伝える
Matterportの最大の特長は、高精度な3Dスキャン技術によって、展示空間全体を立体的に再現できる点です。通常の写真や動画では表現しにくい作品の質感や立体感を、リアルに伝えることができます。
たとえば、以下のような要素も細部まで表現されます。
- ・絵画の凹凸や筆致の陰影
- ・彫刻の形状や陰の動き
- ・空間内の照明や壁の質感
これにより、まるでその場に立って作品を見ているかのような体験が可能になります。さらに、自由に視点を変えて、好きな角度から作品を観察できるため、来館時よりも詳細に観賞することも可能です。
高解像度スキャンによって、作品の魅力をよりリアルに、より深く伝えることが実現されます。
音声・動画・テキストで多層的に作品を解説
Matterportの空間には、音声・動画・テキストといったさまざまな情報を埋め込むことができます。これにより、鑑賞者が自分のペースで作品について学べる「多層的な展示解説」が実現します。
具体的には、次のような活用が可能です。
- ・作品の横に表示される解説テキスト
- ・作者のインタビュー映像を埋め込んだ動画リンク
- ・音声ガイドによるストーリーテリング
展示の背景や作者の意図を深く知ることで、鑑賞者の理解や感動は大きく深まります。また、好みに応じて情報量を調整できるため、初心者から専門家まで満足できる構成が可能です。
単なる鑑賞から「学びと体験」を重視した展示へと進化させることができます。
バリアフリーなオンライン鑑賞体験の提供
Matterportによるバーチャル展示は、年齢や身体的な制限に関係なく、誰でも自由に鑑賞できるバリアフリー性が特長です。移動が困難な方や遠方に住む人々にとって、オンラインでアクセスできる展示は大きな価値があります。
さらに、次のような配慮によって、誰にとっても優しい鑑賞体験が実現します。
- ・画面上の文字サイズや音声ガイドの調整
- ・車椅子目線での視点切り替え機能
- ・聴覚・視覚障がい者向けの字幕・音声サポート
このような機能を組み合わせることで、実際の来館以上に多くの人に配慮した展示が可能になります。特定の時間に制限されることもなく、自分のペースで鑑賞できる点も魅力です。
誰もが等しく芸術や文化に触れられる環境を、Matterportは実現します。
Matterport導入を検討する際のポイント
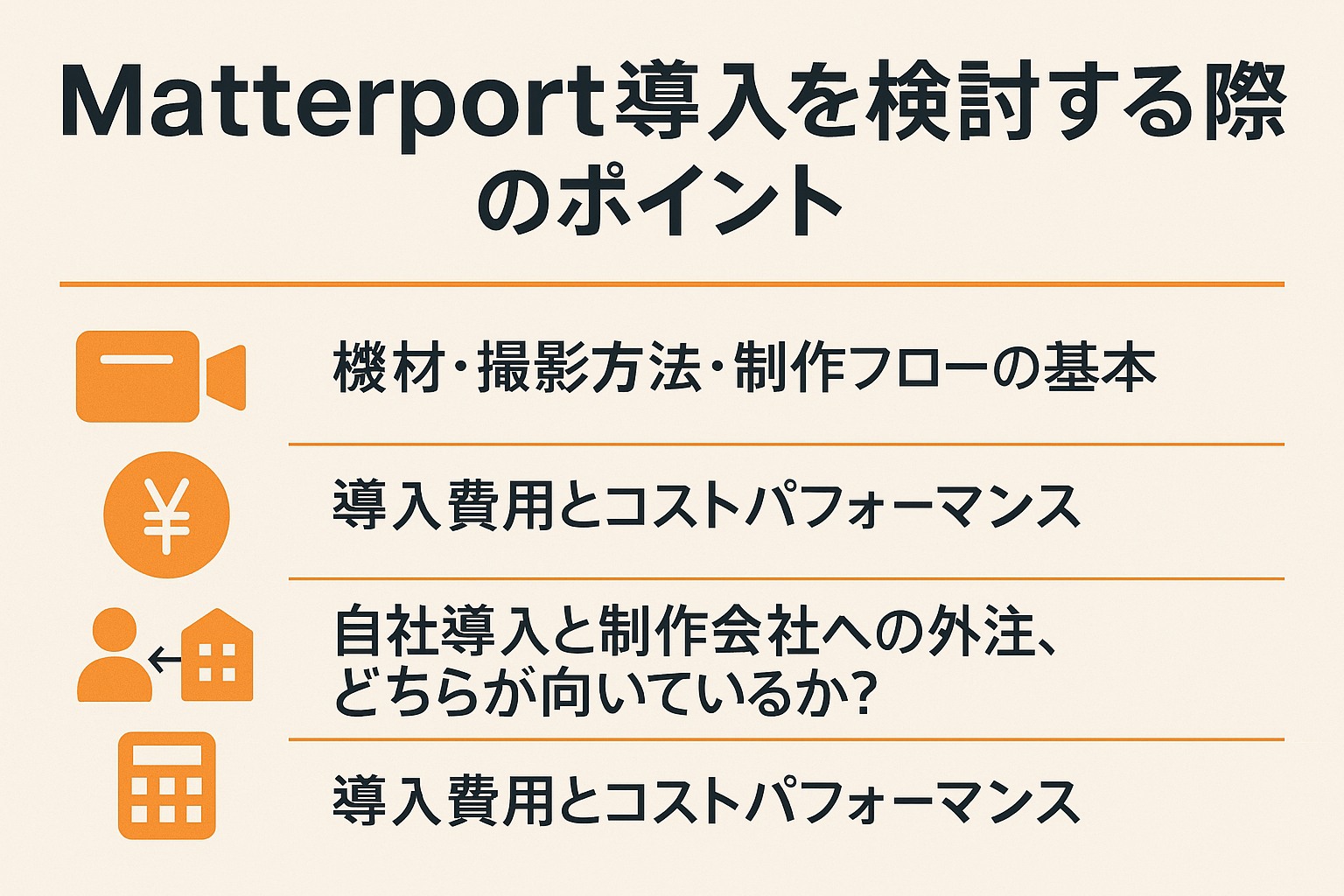
Matterportを美術館や博物館で導入する際には、あらかじめ知っておくべき技術的・経済的なポイントがあります。ここでは、撮影の仕組みから費用感、外注と自社制作の判断基準まで、導入に必要な基本情報を紹介します。
機材・撮影方法・制作フローの基本
Matterportを活用するには、専用の撮影機材とその操作方法、撮影後のデータ編集など、一連の制作フローを理解しておく必要があります。仕組みを把握すれば、運用のイメージが明確になります。
基本的な制作フローは以下のとおりです。
- ・専用カメラまたは対応スマートフォンで空間をスキャン
- ・撮影データをクラウド上のMatterportシステムにアップロード
- ・自動処理によって3D空間が生成される
- ・Webで公開する前に、タグやテキストなどの編集を実施
カメラには、Matterport Proシリーズ(高精度・高価)や、360度カメラのInsta360などが使用できます。スマートフォン撮影にも対応しているものの、展示空間の再現度を重視するなら、専用機材の使用が推奨されます。
正確で魅力的なバーチャル展示を作るには、撮影と編集の基本をしっかり理解しておくことが重要です。
導入費用とコストパフォーマンス
Matterportの導入には、初期費用と運用コストが発生します。しかし、その費用に見合うだけのメリットを得られるかどうかが、導入判断の鍵になります。
主な費用項目は以下の通りです。
- ・カメラ本体(10万円〜50万円程度)
- ・クラウド利用料(月額数千円〜)
- ・外注時の撮影・編集費(1回数万円〜)
一見高額に思えるかもしれませんが、展示の記録保存や広報、教育コンテンツとしても活用できる点を考慮すると、高い費用対効果が期待できます。特に、展示を資産として長期的に活用する方針がある施設には向いています。
初期投資は必要ですが、多面的な活用が可能なため、費用対効果は非常に高いといえます。
自社導入と制作会社への外注、どちらが向いているか?
Matterportの制作は、自館で行う方法と、外部の専門会社に依頼する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、施設の規模や目的によって選択すべき方針が変わります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 比較項目 | 自社導入 | 制作会社に外注 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 機材費が必要 | 1回ごとの費用発生 |
| 柔軟性 | 何度でも自分で撮影可能 | 撮影の都度スケジュール調整 |
| クオリティ | スキル次第で変動 | プロが対応するため安定 |
| 手間 | 操作・編集の習得が必要 | 撮影から編集まで任せられる |
短期的な企画展のみで使いたい場合は外注、年間を通して何度も活用する場合は自社導入が向いています。スタッフのITスキルやリソースも判断材料となります。
運用目的と人的リソースを明確にし、最適な導入方法を選ぶことが成功の鍵です。
よくある質問(FAQ)
Matterportの導入を検討する際には、技術的な疑問や運用上の不安を感じる方も多いはずです。ここでは、よく寄せられる3つの質問についてわかりやすく解説します。
どのような作品でも撮影できるの?
基本的には、展示空間にあるほとんどの作品を撮影できます。ただし、光の反射や透明度が高い素材など、一部の条件では撮影結果に影響が出る場合があります。
たとえば、以下のような作品には注意が必要です。
- ・ガラスやアクリル製の透明な展示物
- ・強い照明で反射する金属や鏡面の作品
- ・非常に小さく細かい造形を持つ立体作品
こうした場合でも、カメラの角度や照明の調整によって、ある程度の再現は可能です。事前にテスト撮影を行い、適切な条件を整えることで、多くの作品を問題なくデジタル化できます。
撮影に適した環境を整えることで、幅広いジャンルの作品を3D展示として公開できます。
展示替えのたびに再撮影は必要?
展示が入れ替わるたびに、Matterportで再度撮影する必要があります。Matterportは「空間そのもの」をデジタル化する技術のため、展示物が変われば、それを正確に反映するためには再スキャンが必要です。
ただし、以下のような工夫をすることで、再撮影の負担を軽減できます。
- ・固定展示部分と企画展示部分を分けて撮影する
- ・毎回の撮影ポイントをテンプレート化しておく
- ・展示替えのタイミングで定期撮影をルーティン化する
常設展示は一度撮影すれば長期間使用できますが、企画展や短期展示の場合は記録として残す意味でも再撮影が推奨されます。
展示内容に応じた適切な撮影計画を立てることで、効率的に運用できます。
セキュリティ面はどうなっている?
Matterportの3Dモデルは、クラウド上に保存されます。アクセス制限や非公開設定が可能なため、セキュリティ面でも配慮されています。インターネット上に自由に公開せず、関係者のみに共有することもできます。
主なセキュリティ対策は以下の通りです。
- ・パスワード保護による限定公開
- ・URLを知っている人だけが閲覧できる「限定リンク」機能
- ・閲覧権限をグループごとに設定
加えて、撮影前に「公開しても問題ない範囲」の確認を行い、必要に応じて一部をモザイク処理することも可能です。展示物に関する著作権や個人情報への配慮も欠かせません。
正しい設定と事前確認を行えば、安全に3D展示を公開できます。
Matterportによるデジタル展示の未来展望
デジタル展示の進化は、単なる「オンラインで見られる展示」の枠を超えつつあります。Matterportは、今後さらに多くの分野と融合し、教育や観光、文化の保存にも影響を与えていくと予想されます。ここでは、今後の展望について詳しく見ていきます。
XR(AR・VR)との融合による可能性
Matterportは、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といったXR技術と組み合わせることで、これまでにない鑑賞体験を生み出します。XRとは、現実世界とデジタル情報を融合させる技術全般を指します。
具体的には、次のような活用が考えられます。
- ・VRゴーグルを使って展示空間を「実際に歩く」体験
- ・ARアプリを通じて現実空間に作品を重ねる表示
- ・バーチャル展示会での双方向型コミュニケーション
来館者が展示空間に没入し、リアルとデジタルが重なり合う体験を得られることで、美術館・博物館の価値が大きく広がります。スマートフォンだけで参加できるXR体験も増えており、一般層への普及も進みつつあります。
XRとの融合は、デジタル展示を「見るもの」から「体験するもの」へと進化させる原動力になります。
教育・観光・文化継承への応用
Matterportで記録された3D空間は、芸術鑑賞だけでなく、教育や観光、文化継承の分野でも活用できます。これにより、単なる展示物の紹介にとどまらず、次世代の学びと社会的価値を提供する道が開かれています。
以下は、具体的な応用の可能性です。
- ・学校教育における「バーチャル遠足」としての導入
- ・観光資源としてのバーチャル美術館ツアー
- ・重要文化財や失われた展示の保存・再現
とくに災害や戦争、経年劣化によって失われる可能性のある文化財を、デジタルで残す手段としてMatterportは有効です。また、地方の小規模施設や地域資料館でも、観光振興と学習教材としての価値を高められます。
デジタル展示は、芸術体験だけでなく、地域・世代・未来をつなぐ社会的インフラとして進化し続けています。
まとめ|Matterportは美術館・博物館の展示体験を革新する
この記事では、美術館・博物館におけるMatterportの活用方法とその効果について解説しました。
①3Dスキャンによるリアルな展示再現
②来館が難しい人への鑑賞機会の提供
③バーチャル展示による集客・教育・文化継承への貢献
④導入における機材・費用・活用方法の具体例
Matterportを導入することで、より多くの人に作品の魅力を伝えることが可能になります。デジタル展示を導入したいと考えている美術館・博物館の方は、この記事の内容を参考に、実現に向けた一歩を踏み出してみてください。
現在、当サイトではMatterportによる360°空間の撮影を無料でを承っております。詳しくは下記よりご覧ください。